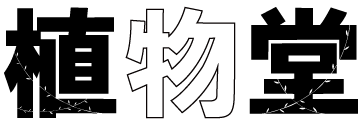「間もなく、2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に……」
ホームに、合図の音と放送が流れる。同時に、ドタバタと駆け下りる複数の足音が階段から響いて来ていた。
「わああっ。鳴ってる、鳴ってる! もーっ、おちゅーがコンビニ寄ったりするから! 一馬くん、先行って止めといて!」
「はいはい」
階段を駆け下りるのは、四人の高校生だった。男子が三人、女子が一人。その内の一人、柊一馬は階段を一段飛ばしで駆け下りて行く。
一番最後に続いている男子が、口を尖らせて言った。
「別にまだ来てないんだし、大丈夫じゃねー?」
「それで、一本前の電車を逃したんだけどな」
眼鏡の男子が、ぼそりと呟く。
「うっ……田宮まで……」
御厨暁、田宮八尋、上原雪乃。彼らは一馬と同じ、地学部の部員だった。先輩も後輩もいない、部員がゼロになりそうな所で一人か二人入る程度で何とか続いて来た部活に、どう言うわけかこの学年では四人の入部があった。とは言え、先輩の勧誘が惹かれるものだったとか、偶然にも地学に興味を持つ生徒が集まっただとか、そう言う素晴らしい理由はなかった。一馬が入部した理由は、ただ単純に、楽そうだったから。
他の部員達も似たり寄ったりである。遊ぶ時間が欲しかった者、塾へ通っている者など。部活動必須の一馬達の高校において、全部活強制活動日の週一回のみしかなく、終了時間も早い地学部は貴重だった。今はもう冬場だと言うのに、まだ空は明るい。
何とか三人も間に合い、電車は駅のホームを滑り出して行った。
「おっ、ラッキー。席、ちょうど四つ開いてるじゃん」
ぽつぽつと空いた席に御厨が声を弾ませ、一番近い二人分空いた席に座る。田宮は真っ直ぐに一人離れた空席へ座り、本を読み始める。
一馬が御厨の隣に座ると、反対隣の女性が席を立った。一馬達が友達連れなのを察し、空いていた席にずれてくれたのだ。
「あ、ありがとうございます。……きゃっ」
電車が揺れ、雪乃の身体がぐらりと傾き、目の前に座る一馬に折り重なった。
「ご、ごめん、一馬くん!」
「大丈夫か、植原?」
「う、うん」
雪乃は慌てて起き上がり、一馬の隣に座る。そして素早く塾の教科書を取り出すと、顔を覆うようにして読みふけり出した。
「田宮も植原も本かよ。つまんねーなー」
「そんなに顔を近付けて読んでたら目悪くなるぞ」
雪乃は答えず、頑なに本で顔を覆っていた。
いつの間に眠ってしまったのだろう。こおお……と風の響くような音で、一馬は目を覚ました。
寝ぼけ眼で辺りを身回そうとしたが、身体を動かす事は叶わなかった。両隣に座る雪乃と御厨が、一馬の肩に寄りかかるようにして眠っていた。雪乃はともかくとして、御厨はあまり嬉しくない。
首だけ動かして見れば、田宮も斜め前の席で眠りこけていた。彼の手にあった本は床に落ちてしまっている。江戸のような街並みが表紙に水彩で描かれた単行本だった。
一馬達の乗る車両に、他の乗客の姿はなかった。窓の外は暗く、一切の光も無い。どうやら、トンネルの中を走っているらしい。
「おい、おちゅー、植原。起きろ」
軽く身をよじり、二人の身体を揺らす。すぐに、二人は目を覚ました。
「ん……あれ? いつの間に寝ちまったんだ……?」
「わっ、ご、ごめん!」
わたわたと雪乃は一馬から離れる。御厨は床に落ちた単行本を拾うと、田宮の頭をパシンと軽く本で叩いた。
「起きろーっ。何だこれ、田宮の奴、四谷怪談なんて読んでたのか」
田宮は目を覚まし、きょとんと辺りを見回す。目をこすろうとした手が、眼鏡に当たっていた。
「ここ、どこ?」
「さあ? 俺もさっき一馬に起こされたところ」
問うように御厨は一馬を振り返るが、一馬も今ここがどこなのかさっぱり検討もつかなかった。
「この辺、トンネルなんてなかったはずよね? どこまで来ちゃったんだろ……一番遠いのって、おちゅー? 田宮?」
「俺」
そう答えたのは、田宮だった。
「でも、俺の降りる駅までも、こんなトンネル覚えがないよ。地下の駅はあるけど……こんなに長くないし、そもそもいくらラッシュと逆とは言えあの駅の前後で無人って事はないだろうしなあ……もしかして、海の方まで来ちゃったのかな」
「何でもいいから、次の駅で降りようぜ。駅に降りりゃ、看板だってあるだろうしどの道反対行きに乗らなきゃだろ」
御厨の言葉が聞こえたかのように、電車は速度を落とし始めた。
音の響きが無くなる。電車がトンネルを抜けたのだ。
そこは、山の中だった。左右の窓の向こうには、土壁が迫る。急勾配となっているそこには、木々が生い茂っていた。
何の放送もなく、電車は停止した。合図の音さえもなく、片側の扉が開く。
御厨が真っ先に降車する。一馬も、彼の後に続いてホームに降り立った。
申し訳程度に改札周りに屋根が付いただけの、小さなホーム。人影は、ない。眠っている内に日も落ち、改札のそばに付いた照明がホームを照らし出していた。
一体どこまで来てしまったのか、改札に見慣れた機械はなく、ただ箱が置かれているだけだった。
「海の近くだとは、とても思えないな……」
田宮がきょろきょろと辺りを見回し、呟く。御厨は、切符を入れる箱を物珍しそうに覗き込んでいた。
雪乃はまだ、車両の中だった。扉を押さえるかのように手をつき、じっと立ち尽くしている。
「どうした? 植原、降りないのか?」
「だって……ねえ、何かヤバイって。駅名も言わなかったしさ……」
「もしかしたら終点も過ぎて、回送でどこかの車庫の方まで来ちゃったのかもな。どちらにしても、そのまま乗り続けてたら更に遠ざかるだけだろ」
雪乃はまだ不安気だったが、渋々と駅に降りた。
途端に、発車合図のベルが鳴り響く。それは曲を奏でるメロディではなく、ジリリリ……と危険を告げるかのような音だった。
「ほら、やっぱり回送だ」
ゆっくりと扉が閉まる。車体は徐々に速度を増し、ホームを滑り出していった。
仄暗いホームに立ち一馬は去って行く電車を見送っていた。この駅は山を切り開いて作られているらしく、行き先にも直ぐトンネルがあった。電車はまるで飲み込まれるように、闇の中へと消えて行った。
薄々勘付いてはいたが、駅舎に駅員の姿はなかった。改札と言う名の箱のそばに窓口はあるが、果たして使われる事があるのか分からない。全くの無人駅である。
「げ。ここ、圏外だ……」
携帯電話を取り出して、御厨が嘆く。一馬達も各々携帯電話を取り出すが、そこにあるのは「圏外」の二文字だけだった。
「ちぇ。GPS使えば、ここがどこなのか分かると思ったのにな」
「まあ、普段使ってる路線沿いはあり得ないな。回送となると、どこをどう走ったのか……」
しばらく四人はホームにいたが、待てど暮らせど電車が来る気配はない。ホーム上をうろちょろしていた御厨も飽きてしまい、ベンチに座り込んでいた。そのベンチも、よく見かけるプラスチック製の物ではなく、公園でたまに見るような背もたれのない木製の長椅子だ。
「これ、もしかして折り返しの電車ないんじゃないか?」
田宮は、一向に来る気配のない電車に痺れを切らしていた。
「回送だったなら、使われていない駅って可能性も……」
「げぇーっ、マジかよ。あーあ、急いであの電車にのったりしなければ……」
「何よ、私のせいだって言うの? 元はと言えば、あんたがコンビニなんて寄って一本逃したから……」
「まあまあ。とにかく、ここで待っていても仕方が無い。駅を出て、人を探そう。少なくとも、ここがどこなのかは分かるだろ。もしかしたら、電車はなくてもバスやタクシーがあるかも知れないし」
「タクシーって、一馬、そんな金持ってんの?」
「まあ、タクシーは最終手段って事で……」
どこだか分からない山奥の駅。見知った町、あるいは在来線の走っている駅まで向かうにしても、どれほどの距離があるか分からない。
改札を通り抜ければすぐに外へ出てしまう小さな駅。駅舎の目の前には、駐在所があった。
「よっしゃ! お巡りさんに聞けば一発じゃん!」
駅前に車通りはない。御厨は道路を斜め横断し、真っ直ぐに駐在所へと走って行く。
道路には、雪が積もっていた。一馬達の地元でも雪が降る事はあるが、ここまで積もりはしない。一体、どこまで来てしまったのだろうか。
駐在所に、警官はいなかった。蛍光灯の明かりが、煌々と無人の所内を照らしている。
窓口の机の上に、地図が広げられていた。等高線に囲まれた村。駅は、その北側に位置していた。四方を山に囲まれ、出入りの手段は電車くらいしかないようだ。
「おおっ、すげー! これって、本物じゃね?」
御厨の手には、拳銃が握られていた。
「ちょっと、バカ! 暴発でもしたらどうするのよ!?」
「おちゅー、元の場所に戻せ」
雪乃と一馬に口々に言われ、御厨は渋々と拳銃を部屋の隅に戻した。
「地図だけだと、どこの村なのか分からないな。ここも電波繋がらないし……」
携帯電話の画面を見ながら、田宮がぼやく。
地図の他にも、現在の居場所を示すようなヒントがないかと、一馬は手近にあった棚に手をかける。しかしそこは、鍵が掛かっていて開けられなかった。
「仕方ない。ここにいても警官が戻って来る気配はないし、他に人のいそうな場所を探してみよう」
地図を見れば、すぐ近くに村役場があるとの事だった。こんな時間だと、もう閉まっているかも知れない。ダメ元で行ってみた村役場は、駐在所と同じく煌々と明かりがつき、そして駐在所と同じく無人だった。
「誰もいないな……」
「仕方ない。また別の所を……」
動いた一馬の手に触れ、ばさばさと何かが机の上から崩れ落ちた。
それは、新聞紙の山だった。日付を見れば、1997年。相当古い新聞だ。
「集団自殺か? 小学生八人死亡……」
一馬は何の気なしに、見出しを読み上げる。
その時、フッと明かりが消え、室内は闇に包まれた。
「きゃっ、な、何!?」
雪乃が短い悲鳴を上げる。
「誰か閉めに来たのかも」
「あっ! 外、誰かいるみたいだぜ。こっちに来る」
窓際にいた御厨が、外を見て言った。
「良かった、その人に事情を話して帰り道を教えてもらおう」
一馬の一言で、四人は入って来る人物を迎えに玄関口の方へと向かった。
暗闇の中を、手探りで進む。幸い月明かりもあり、特に窓の広い玄関口では辺りをはっきりと見て取る事が出来た。
「すいませーん、俺達、迷子になっちゃって……」
例によって御厨が真っ先に駆け寄ろうとしたが、入って来た姿を見て彼は足を止めた。
年老いた老人だった。とは言っても、背中はまだ真っ直ぐに伸びている。それだけなら、村長か何か関係者だと思っただろう。
真冬だと言うのに半袖のポロシャツを見にまとい、その下から覗く腕は、骨と皮のようだった。――そして。
彼の眼孔に瞳はなく、ぽっかりと空いた闇が一馬達を見つめ返していた。
「きゃあああああああ!!」
耐えきれなくなった雪乃の悲鳴が迸る。
凍りつくように立ちすくんでいた男子三人も我に返り、建物の奥へと駆けて行く。
老人はだらりと腕をこちらに伸ばし、滑るように後をついて来た。
「何!? 何なのよ、今の!?」
雪乃が半泣きで叫ぶが、その問いに答えられる者はいない。
四人は突き当たりの部屋に飛び込むと、内側から鍵を掛けた。
「鍵なんて意味あるの?」
「分からないけど、無いよりマシだろ!」
激しい口調で答え、一馬は室内に目を走らせる。
奥に小さな窓があるのみ。ここから抜け出すなら、直ぐにもよじ登らなくてはならないだろう。この場で得体の知れないモノと根比べなんて御免だ。
三人をそちらへ促そうとしたその時、パァンと破裂音のような音が廊下で響いた。
「こ、今度は何!?」
「銃声みたいだったけど……」
一馬達は顔を見合わせる。外で、一体何が起こっているのだろうか。
コンコンと扉を叩く音がして、四人は跳ね上がった。
「開けて。弾を無駄にしたくない」
聞こえて来たのは、女の子の声。一馬は部屋の奥にある小窓を少し振り返る。この距離であの狭い出口。到底逃げられる状況ではない。
それに何より、女の子の声は静かだが力強く、助けを期待せずにはいられなかった。
一馬はそっと、ドアノブの鍵に手を掛ける。
「ちょ、ちょっと! 開けちゃうの?」
「どちらにせよ、逃げ道がない」
戦々恐々と開いた扉の先にいたのは、セーラー服を着た小柄な女の子だった。白い肌に、肩で切りそろえた黒い髪。手には、猟銃を持っている。さっきの銃声は、これによるもののようだ。
女の子は大人しそうな雰囲気にそぐわず、きびきびと言った。
「急いで。壊しただけだから、直ぐまた動き出す」
そう短く言うと、くるりと一馬達に背を向けて足早に歩き出す。
「え、あ、おい!」
一馬の呼び止める声も聞かず、彼女はスタスタと歩いて行ってしまう。後を追おうとした一馬の服を、雪乃が掴んだ。
「ついて行くの……?」
答えたのは、御厨だった。
「そりゃ、行くだろ。他に当てもないし、元々人を探してたんだし。助かったじゃん」
「もー、あんたはほんっと、のんきね! 助かったとは限らな……」
「あんまり騒がない方がいいと思うよ」
田宮は、廊下の先を顎で示す。
そこには、先程の老人がうつ伏せに倒れこんでいた。御厨が恐々とそちらを覗き込むように首を伸ばす。
「……し、死んでんの、これ?」
「さあ……あの子は、壊しただけだから直ぐまた動くって言ってたけど……」
「って、あの子行っちゃうじゃん!」
猟銃の女の子は、玄関口の方へと曲がって行ってしまう。一馬達は慌ててその後を追って駆け出した。
「あっ。ちょっと! 待ってよー!」
三人が走り出し、雪乃も渋々後を追って行った。
建物を出て階段を下りた先で、女の子は待っていた。
「この建物はダメ。あの人が、ずっとうろついてるから。たぶん、村長か何かだと思う」
役場を見上げて、少女は言う。御厨が、恐る恐る問うた。
「えーっと、さっきのあれって……」
「あなた達が見た通りの事しか、私も知らない。人を見つけたら、襲って来る。頭や足を撃てば足止めは出来るけど、死ぬ事はない。そう言う死体って事になるのか、また動けるようにもなる。少なくとも、生きた人間ではないと思う……」
「や、やっぱり? ですよねー……」
「君は、一体……?」
一馬の問いに、彼女は振り返った。短い髪が、風に揺れる。
「平坂琴。たぶん、私とあなた達は同じ。気付いたら、この村に迷い込んでいたの。……もう、ずっと帰れないまま」
村を囲む山の木々が、ざわざわと葉を揺らす。
それは、これから始まる不気味な物語の予兆を告げているかのようだった。